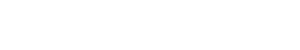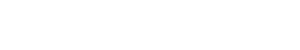| |
会長会見 2006年04月17日
(小枝会長)
販売と生産について
- 2005年度の国内販売は586万台・前年比100.7%。景気指標が改善されているのにクルマの販売が伸びないのは、我々が魅力ある商品を充分出していないためで、今後を期待していただきたい。
- 生産は、国内が1千万台、海外も1千万台でトータル約2千万台。自動車の年間のグローバルな生産・販売は約6千万台なので、日本メーカーが3分の1を占め、大変な成長をしていると言える。
- 国内生産1千万台は、部品メーカー、資材メーカーと協力して努力した結果と思う。世界での競争力確保のためには、国内の基盤確保は最重要である。
道路特定財源に関する活動について
- 昨年はお客様の関心も高まり、署名活動や街頭活動を行なった結果、1カ月で240万人の署名をいただいた。
- 我々としては今年が勝負の年だと思っており、この6月に骨太の方針が出る前に、政府の方針決定に我々の正当な主張を取り入れていただくべく活動をしていきたい。
任期2年を振り返って
- この2年間、2つを柱に活動をしてきた。
- ひとつは「お客様や社会にとって我々自動車産業が役立つことは何か」を念頭においた活動である。自動車として求められているのは、安全と環境への取り組み。自動車リサイクルシステムの稼働に向けた取り組みや、燃費改善やクリーンエネルギー車の積極的な開発を行ってきた。またリコール隠しによりリコール制度自体が信用をなくすのではないかと心配したが、お客様には冷静に対応していただいており、感謝している。
- 2点目は「日本を基盤とした産業」であること。日本を基盤にするのは、お客様の要求が世界一厳しくて鍛えられ、強力な資材産業、部品産業その他関連産業に支えられているから。部品メーカー・関係業界のサポートや我々の努力により、1千万台の国内生産を続けることが出来たことは、大変印象に残っている。
トラックメーカーを巡る自動車業界再編について
- 自工会が関知することではなく、それぞれの会社の判断であるので、自工会会長としてコメントする立場にない。
- これらの動きが大変動になるかどうかはわからない。この先の動向を注視したい。
米国燃費基準強化について
- 最近決定したのはトラックの燃費基準だが、CO2削減の面ではリーズナブルな決定だと思う。
- 現行より基準がかなり厳しくなっているので、燃費対策の努力が必要。
原油価格高騰の影響について
- 原油高騰の影響は遅効性があるので、いま急にどうということはない。
- 今後の影響としては、小さいクルマを買おうかという心理的な影響と、資材の価格が順次上がっていくという産業全体の影響の2つがある。
- バイオマスなどの代替燃料もあるが、オイルシェルなど石油自体の他の供給源も出てくるので、全て石油から他の燃料に切り替わることは直ぐにはないと思う。
国内・海外生産台数の拮抗と経営課題について
- 日本の自動車メーカーは国内1千万台、海外1千万台の計2千万台を生産しているが、そのうち6百万台が国内で売れていて、1千4百万台は海外で売れている。商品計画はお客様に合わせるものであり、少なくとも最終の組立はお客様の近くで行うのが原則だから、この傾向は続くと思う。
- 日本の自動車産業の強みのひとつは「日本ブランド」であること。日本で開発・生産をやっているため、品質や先端技術などの競争力が備わり、世界で競争していける。
- もうひとつ重要な点は「お客様に近いところでお客さんに合った経営をしないと発展しない」ことであり、会社自体のグローバル化は急速に進んでいくと思う。
|